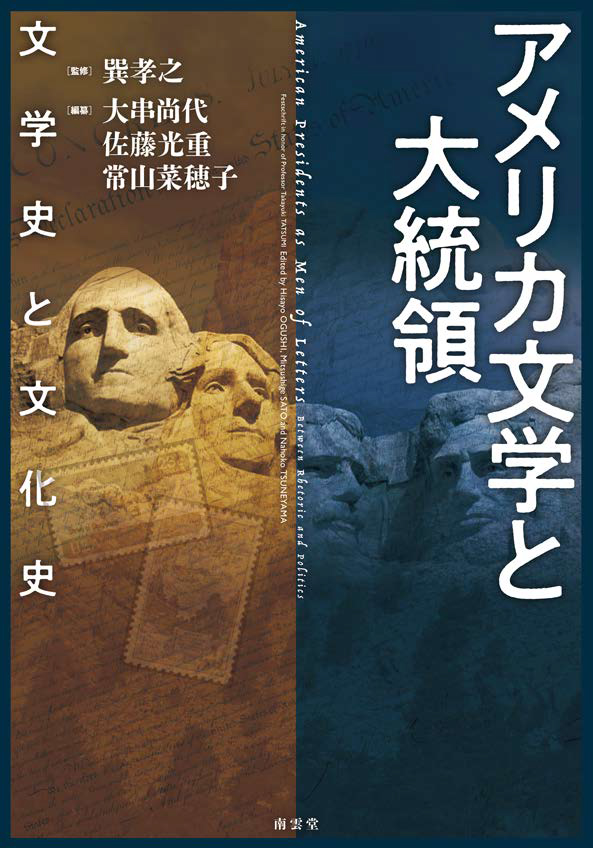ASLE-Japan/文学・環境学会設立30周年を記念した書籍が、来月刊行されます。私は、現代日本文学における「猫」表象の困難さを論じた「隠喩としての猫を棄てる──動物愛護管理にまつわる構造的暴力と作家の倫理的選択」を寄稿しました。書店等でぜひお手にとってみてください!
ブログの説明
3/27/2025
【論考】「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」論
法政大学英文学会発行の『英文學誌』(第67号)に拙論が掲載されました。タイトルは「監獄大国アメリカを生きる:原作を改変した『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』はいかに現実を変革したか」(pp.1-16)です。
3/19/2025
【連載】『ネトフリで知るアメリカのリアル』
***
【各章で言及されている主なコンテンツ】はじめに
・『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』(2013-19)
・『ROMA /ローマ』(2048)
・『イカゲーム』(2021-)
Ch.1「働けどなお、わがくらしミドルにならざり」
・『トランプ:アメリカン・ドリーム』(2018)
・『ダマすが勝ち! ブルシット』(2022)
・『メイドの手帖』(2021)
・『アメリカン・ファクトリー』(2019)
・『ヒルビリー・エレジー』(2020)
3/15/2025
【予告】Web連載が始まります!
気づけば新学期も目前。皆様いかがお過ごしでしょうか?
研究や批評にも仕込みの時間が必要ですが、この半年でようやくその一部が収穫の頃合いとなりました。
まずは来週から、立東舎さんの公式サイトにて、書き下ろし批評の連載が始まります。
タイトルは「ネトフリで知るアメリカのリアル」。
選挙、労働、薬物、監獄、差別……といった主題を、Netflixのコンテンツはどのように物語化してきたのか。
初回は【3月19日】に公開予定ですので、ぜひご一読ください!
立東舎HP「コラム」→ https://rittorsha.jp/column/categorylist.html
8/10/2024
ASLE-Japan学会誌が発行されました

7/25/2024
8月はオープンキャンパスへ!
法政大学では、8月9日〜10日にオープンキャンパスと模擬授業を実施します。ぜひ、この機会にキャンパスの雰囲気と授業のおもしろさを体感してみてください。
*無事終了しました! ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
* * *
▶︎文学部の模擬授業
8/10
哲学科(内藤 淳 教授)「もしも法がなかったら……:法哲学で考えること」
日本文学科(加藤 昌嘉 教授)「『源氏物語』とはどういうものか?」
英文学科(波戸岡 景太 教授)「モブキャラは物語の主人公になれないのか?」
史学科(齋藤 勝 准教授)「中国の歴史と民族・文化」
地理学科(小原 丈明 教授)「都市問題を地理学から考える」
心理学科(高橋 敏治 教授)「記憶力アップには睡眠が重要」
7/24/2024
春学期のふりかえり
法政大学に移籍してはじめての春学期が終わりをむかえつつあります。この4か月は、新たな学生さんたちとの出会いに刺激を受けながら、めまぐるしく変化する時代に向き合うための「テクスト」を読み解く毎日でした。以下は、2024年の春学期にそれぞれの授業で扱った主な教材一覧です。
▶︎英米文学演習(学部ゼミ)
・ミシェル・ザウナー『Hマートで泣きながら』韓国系アメリカ人のメモワール
・ジーン・ルエン・ヤン『アメリカン・ボーン・チャイニーズ』中国系アメリカ人の自伝的グラフィックノベル
・ジュリー・オオツカ「Diem Perdidi」『スイマーズ』認知症をモチーフにした日系アメリカ人の短編小説
・映画『ムーラン』ディズニー映画のアニメ版と実写版
▶︎英米文学講義
・リオタール『ポストモダンの条件』
・ソンタグ『隠喩としての病い』
・ソンタグ『反解釈』
・ヴォネガット『スローターハウス5』
・ピンチョン『重力の虹』
・ベン・ブラット『数字が明かす小説の秘密』
▶︎2年次演習
・野口久美子『インディアンとカジノ』現代のネイティヴアメリカン文化を知るための必携の書
・ニコラス・ピレッジ『カジノ』スコセッシ監督によって映画化されたノンフィクション
・「アメリカ独立宣言」1776年の原文
・映画『ポカホンタス』ディズニー・アニメ
・シャーマン・アレクシー「グリーン・ワールド」ネイティヴ・アメリカンの著者による寓話
4/01/2024
新学期(移籍のお知らせ)
こんにちは。
いよいよ2024年度の始まりですね。
私は、17年間通った明治大学の生田キャンパスを離れ、本日より、法政大学の市ヶ谷キャンパスがホームとなります。
所属は、同大学文学部英文学科。
英米文学講義(今年度はポストモダン文学)や英米文学演習(今年度はアジア系アメリカ文学)などを担当します。
学生さんたちのキャンパスライフが少しでも充実するよう、私なりにできることをしていけたらと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2024年4月1日 波戸岡景太
1/13/2024
【ソンタグ本】朝日新聞、毎日新聞で紹介されました。
とても嬉しいことに、本日、朝日新聞と毎日新聞の両紙で、拙著『スーザン・ソンタグ』(集英社新書)の書評が掲載されました。評者の三牧聖子先生、橋爪大三郎先生、ありがとうございます。
・朝日新聞「好書好日」
https://twitter.com/BOOK_asahi_com/status/1745951994316263893
「『反解釈』『写真論』『他者の苦痛へのまなざし』等を著し、挑発的な議論を続けたスーザン・ソンタグは、今こそ顧みられるべき人物だ」(三牧聖子氏)・毎日新聞「今週の本棚」
https://twitter.com/mainichi_books/status/1746036436527452405
「スーザン・ソンタグは、半世紀ほど前に一世を風靡したアメリカの知識人。最先端の感性とひと筋縄で行かない思考回路をそなえている」(橋爪大三郎氏)1/04/2024
【新刊】Peter Lang社より共著が刊行されました。
- Part I Image
- 1 Snowflakes and Shadows: Giordano Bruno after Dick Higgins
- 2 The Grain of the Voice and the Materiality of the Digital Image in Alain Cavalier’s Irène (2009)
- 3 Intermedial Post-Romanticism: W. G. Sebald’s Ruins of Empire in Austerlitz (2001)
- Part II Music
- 4 The Imaginaire of Music and the Representation of Emotions in Lev Tolstoy’s Novel Childhood
- 5 Sound of Adaptation: Jaws (1975) and Psycho (1960)
- ‘Water Schools’
- Part III Language/Text
- 6 In-Between Languages, Words and Images: Yoko Tawada’s The Naked Eye
- 7 Image and Text in Multimodal Texts: Intermediality between Visual Images and Japanese Writing Systems
- Part IV Barthes
- 8 Roland Barthes’s Intermedial Practice of Life Writing: Collecting (Auto-)Biographemes, between Image and Text
- 9 Barthes’s Bunraku: An Intermedial Approach to Alterity
- Peter DayanAfterword: Barthes, Fortunately, Had Never Heard of What We Call Intermediality
12/15/2023
【対談】記事が公開されました。
10月29日に開催された書店イベント『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』刊行記念対談(都甲先生&波戸岡)が、集英社新書プラスのウェブサイトに公開されました。お時間のあるときに、ぜひご一読ください!
12/07/2023
【論点】『群像』新年号に寄稿しました。
10/17/2023
【本日発売】『スーザン・ソンタグ 「脆さ」にあらがう思想』
10/12/2023
【告知】トークイベント(10月29日)
来週発売となる拙著『スーザン・ソンタグ:「脆さ」にあらがう思想』の記念イベントを、今月末、三鷹の素敵な書店 UNITÉで開催します。お相手いただくのは、アメリカ文学研究者の都甲幸治先生。都甲先生には最新の世界文学事情もお伺いしつつ、いまなぜソンタグなのかをトコトン語り尽くす90分にしたいと思います!
************************
刊行記念イベント
「生誕90周年! 今こそスーザン・ソンタグ入門」
登壇者:波戸岡景太、都甲幸治
日時:10月29日(日)18:30スタート
【来店参加】 https://unite-books.shop/items/65277fc1808e2c002d9449df
【オンライン参加】https://unite-books.shop/items/65277fff029af10033fa21c5
10/06/2023
【論考】『群像』11月号発売
本日、10月6日発売の『群像』11月号に、古川日出男さんの最新小説『の、すべて』をめぐる論考が掲載されました。1001枚の古川ワールドを読み解く、最初の一手となることを願っています。同時掲載のロングインタビュー(聞き手は小澤英実先生)も、とても楽しみです!

群像2023年11月号(10月6日発売)
https://gunzou.kodansha.co.jp/indexes/1869
〈『の、すべて』 刊行記念〉
- 「デッドエンドな未来の出口を探す」古川日出男(聞き手:小澤英実)
- 「文学(と政治)のためのMission:Impossible——古川日出男『の、すべて』を読む」(波戸岡景太)
9/16/2023
【予告】新書の目次と内容紹介が公開されました。
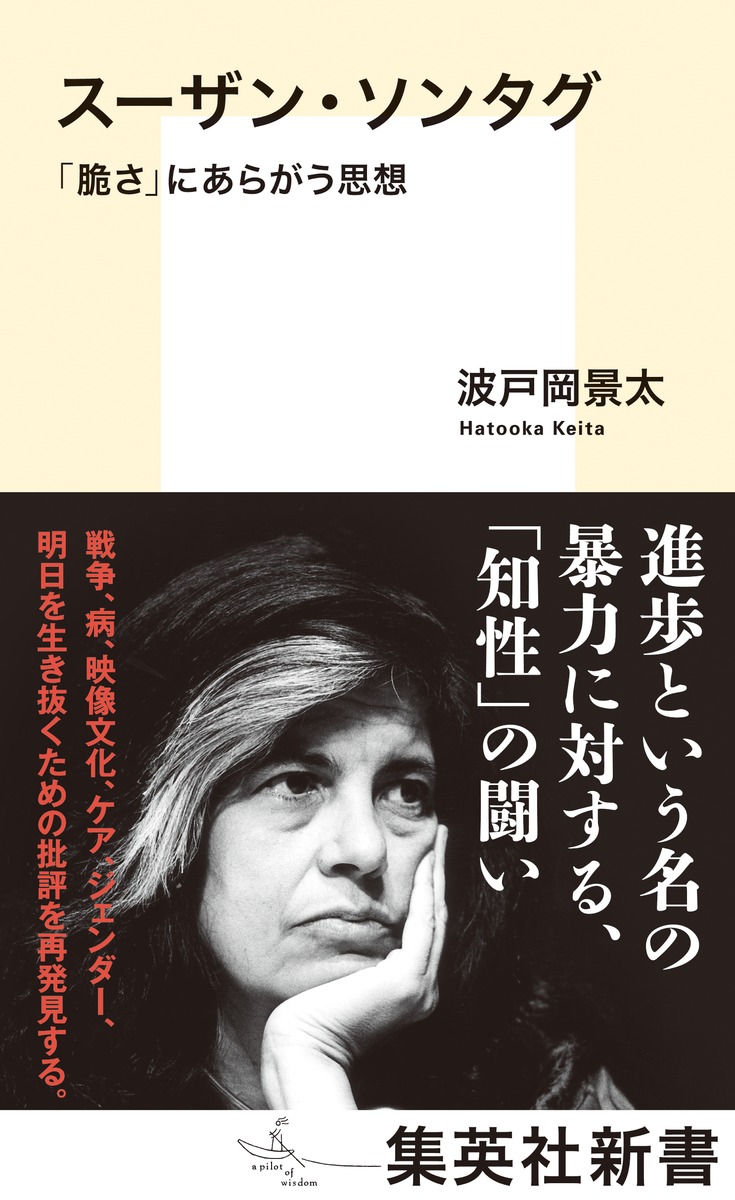
はじめに
第1章 誰がソンタグを叩くのか
第2章 「キャンプ」と利己的な批評家
第3章 ソンタグの生涯はどのように語られるべきか
第4章 暴かれるソンタグの過去
第5章 『写真論』とヴァルネラビリティ
第6章 意志の強さとファシストの美学
第7章 反隠喩は言葉狩りだったのか
第8章 ソンタグの肖像と履歴
第9章 「ソンタグの苦痛」へのまなざし
第10章 故人のセクシュアリティとは何か
第11章 ソンタグの誕生
終章 脆さへの思想
おわりに
9/12/2023
【10月発売】『スーザン・ソンタグ:「脆さ」にあらがう思想』(集英社新書)
7/28/2023
【新刊】『アメリカ文学と大統領』
共著『アメリカ文学と大統領』(南雲堂)が、ついに発売されました。私の担当はニクソンです(第17章「チェッカーズ・スピーチをもういちど:犬とニクソンの伴侶種宣言』)。重厚な一冊、夏休みのおともにぜひ!
歴代大統領とともにアメリカ文学史を駆け抜ける!!
1789 年4 月、ジョージ・ワシントンが大統領就任演説を行なって以降、アメリカの歴史はつねに大統領とともにあった。行政府の長であり、米軍の最高司令官である彼らは、同時に国を表すアイコンであり、アメリカ的想像力の源でもあった。時代毎の大統領が書き残してきた日記や手記、演説原稿、手紙や政治的文書の一群は、アメリカン・ナラティヴの系譜と不可分である。大統領をも文学者とみなし、大統領の歴史と文学思想史のスリリングな共犯関係を追い続けてきた巽孝之教授の退職記念論文集である本書では、教授の薫陶を受けた26 名の研究者が参集し、全く新しいアメリカ文学史のかたちを切り拓く。(版元HPより)
【監修】
巽孝之
【編纂】
大串尚代/佐藤光重/常山菜穂子
【執筆陣】
小泉由美子/大串尚代/大和田俊之/佐藤光重/冨塚亮平/田ノ口正悟/竹野富美子/白川恵子/松井一馬/細野香里/常山菜穂子/奥田暁代/辻秀雄/山根亮一/加藤有加織/濟藤葵/波戸岡景太/麻生亨志/有光道生/中垣恒太郎/秋元孝文/深瀬有希子/長澤唯史/志賀俊介/鈴木透
【コラム】
宇沢美子/内田大貴/榎本悠希
A5 判上製 510 ページ 定価(本体5,800 円+ 税)
ISBN978-4-523-29333-0 C3098
3/25/2023
【新刊】『批評理論を学ぶ人のために』
構造主義から翻訳論までを射程に入れた入門書『批評理論を学ぶ人のために』(小倉孝誠・編)が、来月(4月20日)世界思想社より刊行されます。私の担当は、環境と文学の関係を批評する「エコクリティシズム」。ASLE(文学・環境学会)の設立から、人新世なる概念の誕生にいたるまでを概観しつつ、章の後半では、林京子と古川日出男のテクストを用いて、私なりのエコクリティシズムを実践しています。機会がありましたら、ぜひご一読ください。
目次
はじめに
Ⅰ 記号と物語
第1章 構造主義(下澤和義)
第2章 物語論(赤羽研三)
第3章 受容理論(川島建太郎)
第4章 脱構築批評(巽孝之)
◆コラム 法と文学(川島建太郎)
Ⅱ 欲望と想像力
第5章 精神分析批評(遠藤不比人)
第6章 テーマ批評(小倉孝誠)
第7章 フェミニズム批評(小平麻衣子)
第8章 ジェンダー批評(小平麻衣子)
第9章 生成論(鎌田隆行)
◆コラム 研究方法史の不在(小平麻衣子)
Ⅲ 歴史と社会
第10章 マルクス主義批評(竹峰義和)
第11章 文化唯物論/新歴史主義(山根亮一)
第12章 ソシオクリティック(小倉孝誠)
第13章 カルチュラル・スタディーズ(常山菜穂子)
第14章 システム理論(川島建太郎)
第15章 ポストコロニアル批評/トランスナショナリズム(巽孝之)
◆コラム 文学と検閲(小倉孝誠)
Ⅳ テクストの外部へ
第16章 文学の社会学(小倉孝誠)
第17章 メディア論(大宮勘一郎)
第18章 エコクリティシズム(波戸岡景太)
第19章 翻訳論(高榮蘭)
◆コラム 世界文学──精読・遠読・翻訳(巽孝之)
あとがき
参考文献
事項索引
人名・作品名索引













%20%20%E6%B3%A2%E6%88%B8%E5%B2%A1%20%E6%99%AF%E5%A4%AA%20%E6%9C%AC%20%20%E9%80%9A%E8%B2%A9%20%20Amazon.png)